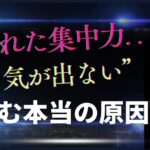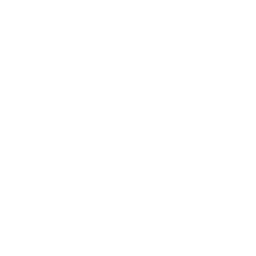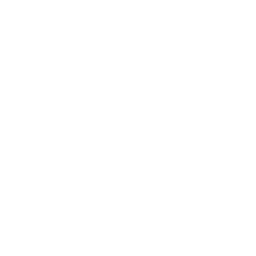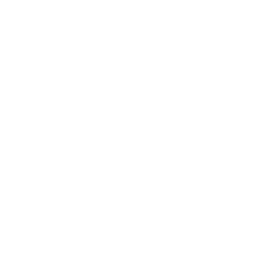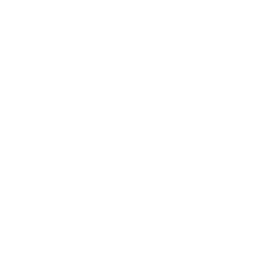理不尽と戦うな、理不尽の中で戦え。―不動産仲介で必ず出会う“納得いかない現実”との向き合い方―
はじめに ― なぜこのテーマを書くのか
不動産仲介という仕事に就くと、誰もが一度はこう思うはずです。
「え、なんでこんな理不尽なことが通るの?」
「こっちはちゃんとやってるのに…」
「もう、こっちのせいにされるのおかしくないか…?」
契約のスケジュール、銀行や士業の動き、売主・買主の温度差、他社の対応のクセ。
不動産仲介は、さまざまな立場の“正義”と“ルール”が交錯する現場です。
中立的な立場に見えて、実はあらゆる責任がこちらに降ってくる。
そう――まさに「理不尽の交差点」にいるのが、不動産仲介の現場です。
特に新人や若手のうちは、こうした“納得できない現実”に何度も直面します。
最初は「何が正しいのか」を見極めようとするけれど、やがて「正しいことを主張しても通らない」ことがあると知り、自分の判断に自信を持てなくなったり、気持ちが萎えてしまうこともあるでしょう。
ですが、これは「あなたが未熟だから」でも「気が弱いから」でもありません。
そもそもこの業界には、“理不尽を避けて通れない構造”があるんです。
大切なのは、それを「理不尽だから嫌だ」と避けるのではなく、「理不尽とどう向き合うか?」という視点を持つこと。
この記事では、
✅ 理不尽とは何か?
✅ なぜ理不尽は起こるのか?
✅ その中でどう立ち回ればいいのか?
✅ 本当にプロと言える営業は、どんな姿勢でこの現実と向き合っているのか?
これらをテーマに、「理不尽の中で戦う」ためのマインドセットを言語化していきます。
理不尽はなくならない。でも、理不尽に振り回されずに立ち回る力は、確実に鍛えられる。
不動産仲介の現場で、自分を見失わずに成長していくためのヒントになれば幸いです。
理不尽とは何か?

そもそも「理不尽」とは何でしょうか?
辞書的には、「筋が通っていないこと」「道理に合わないこと」と説明されますが、不動産仲介の現場において感じる“理不尽”は、もう少し複雑で、もう少しリアルです。
たとえば…
- 銀行から突然「この案件、通せません」と言われた(昨日まで何も言われてなかったのに…)
- 売主側の業者がこちらの確認もなく勝手にスケジュールを組んでいる
- お客様が契約直前になって「やっぱりやめようかな」と言い出す
- 上司から「それ、確認してないの?なんで?」と詰められる(確認したけど相手が変わっただけなのに…)
このような場面に出くわしたこと、あなたにも経験はあるのではないでしょうか。
理不尽とは、「正義のぶつかり合い」である
理不尽の本質とは、「自分のルールや常識が、他者のルールと交わらない状態」です。
たとえば、あなたの中では「契約は当事者間での合意があればスムーズに進むべきだ」という常識があったとしても、銀行側からすれば「その合意はまだ書類が足りていない=成立していない」というルールがあったりします。
お客様にとっての「当たり前」と、
売主業者にとっての「当たり前」、
司法書士にとっての「当たり前」、
あなたの会社にとっての「当たり前」、
――それぞれが微妙に、でも確実に違っている。
この“ズレ”が積み重なると、「なんでそんなこと言うの?」とか「それはおかしいでしょ」という不満になり、やがて“理不尽”と感じるようになります。
不動産仲介は、まさに“正義の中間地点”
不動産仲介の仕事は、売主・買主・他社業者・銀行・司法書士…
それぞれの立場に立ってやり取りをする、いわば“交通整理係”のような存在です。
でも、これはただの仲介じゃありません。
全員がそれぞれの「ルール」と「正義」を持っていて、それが毎回微妙に違う。
その中間に立たされて、調整・翻訳・提案をしなければいけないのが、不動産仲介の本質です。
言い換えれば、不動産仲介とは “正義と正義の狭間”に立ち続ける仕事なのです。
だから、理不尽が起こるのは「想定外」でも「例外」でもなく、ほぼ日常的なこと。
逆に言えば、「理不尽が起きた=誰かが悪い」と考えてしまうと、冷静さを失います。
「自分が正しい」が最も危うい
理不尽を感じるとき、人は無意識に「自分が正しい」と思っています。
でも、その“正しさ”もまた、あなたの立場や経験から生まれたものに過ぎません。
「自分の正義が絶対」だと思うと、目の前の相手の言動がすべて“間違い”に見えてしまいます。
でも、相手もまた自分の正義で動いています。
不動産の現場で理不尽が起こるのは、誰かが悪いのではなく、構造的に起こるべくして起きているのです。
理不尽とは、“戦うべき相手”ではなく“理解すべき現象”
だからこそ、「理不尽」とは戦う相手ではありません。
怒るよりも、悲しむよりも、まず「そういうもんだよな」と受け止めること。
そのうえで、「じゃあ自分はどう動くべきか?」を冷静に考えることが、プロとしての最初の一歩です。
なぜ理不尽は起こるのか? ― 不動産仲介という仕事の“構造的背景”

理不尽を感じるたびに、「なんでこんなことになるんだ…」「こっちのせいにされるのおかしくないか?」と悩む・・・
でもそれは、あなたのやり方が間違っているからでも、誰かが悪意を持っているからでもありません。
そもそも不動産仲介という仕事は、理不尽が起きやすい構造そのものの中で成立しているんです。
不動産仲介は「多者利害調整型」の仕事
まず、不動産取引に関わるプレイヤーをざっと挙げてみましょう。
- 買主(顧客)
- 売主
- 相手側仲介業者(自社ではない)
- 金融機関(融資)
- 司法書士
- 火災保険会社
- リフォーム業者 etc…
- そして自社(あなた自身)
これらすべての人・組織が、それぞれ異なる立場・役割・目的・スピード感・判断基準で動いています。
しかも、そのすべてをひとつの「取引」=契約・決済というゴールに向かわせなければならないのが、仲介営業の仕事です。
つまり、もともと「理不尽が起きない方がおかしい」くらいの構造なのです。
それぞれが“自分の正義”で動いている
- 売主側は「高く早く売りたい」
- 買主側は「安く、慎重に買いたい」
- 銀行は「リスクを最小限にしたい」
- 司法書士は「法的に整合性ある書類が揃っているか」を見ている
- あなたの上司は「今月数字いけるのか?」を見ている
- そしてあなた自身は「全員が納得した上で無事に契約したい」と思っている
それぞれが正しい。でも、それぞれの“正しさ”は交わらない。
これがまさに、理不尽が起きる温床です。
自分でコントロールできない“変数”が多すぎる
不動産仲介の仕事は、調整・段取り・確認が重要ですが、そのすべてにおいて“他人の判断”が入り込むため、完璧にコントロールできることは非常に少ないのが現実です。
たとえば:
- 契約日直前で金融機関の融資承認が遅れる
- 売主が「やっぱりこの日じゃダメ」と言い出す
- 他社の担当者が急に異動して引き継ぎがうまくいっていない
- お客様が親に相談した結果、真逆の意見になった
- 書類を渡したと思っていたら「そんなの聞いてない」と言われる
こうした出来事に、論理や正論は通用しません。
自分は間違っていない。それでも、振り回される。
これが、現場で理不尽を感じる根本的な構造です。
理不尽は、「個人の問題」ではなく「構造の必然」
新人の頃は、理不尽が起きるたびに
「自分の伝え方が悪かったのかな」
「確認が甘かったのかもしれない」
「やっぱり営業向いてないのかも」
と、つい自分を責めてしまいがちです。
でも、冷静に振り返るとわかるのは――
あなたがどんなに丁寧にやっていても、他者の動きひとつで“理不尽”は起き得る、ということ。
つまり、理不尽は「あなたのせい」ではなく、「多者の正義がぶつかる構造」の中で必然的に発生する現象なのです。
「理不尽=異常」ではなく「理不尽=前提」として捉える
これが不動産仲介のリアルです。
だからこそ、大切なのは「どうすれば理不尽をなくせるか」ではなく、「どう理不尽と共存していくか」という視点に切り替えること。
理不尽は、感情的にぶつかっても消えない。
自分が正しくても、状況は好転しないこともある。
でも、あなたの立ち振る舞い次第で、信頼や評価、そして売上という結果は大きく変えられる。
この視点が重要です。
理不尽と“戦って”はいけない理由

理不尽な状況に出会ったとき、そのまま、正面から“戦おう”としてしまう。
しかし、不動産仲介という仕事において、理不尽と真正面からぶつかっても、たいてい報われません。
むしろ、状況を悪化させてしまうことすらあります。
ここでは、その理由と背景を、いくつかの観点から解き明かしていきます。
理不尽に「正論」は通じない
不動産仲介で直面する理不尽は、論理や合理性の外側にある現象です。
たとえば:
- 「昨日は大丈夫って言ってたじゃないですか!」
- 「そんな条件、事前に聞いてませんでしたよね?」
- 「普通ならこうしますよね?」
仮にこれらの主張が“正しい”としても、それで相手が納得したり、状況が好転するとは限りません。
むしろ相手も、
「いや、ウチはウチのルールなんで」
「私はそう聞いてない」
「ウチではそういうやり方してないんです」
と、自分の正義で返してくる。
正論 vs 正論のぶつかり合いが生まれ、出口がなくなっていきます。
「なぜわかってくれないんだ」は通じない世界
あなたの中には「当たり前」でも、相手にとっては「当たり前ではない」。
- 自社の常識が、他社の非常識
- 業界的には当然は、お客様からすると異例
- 上司の指示が、実務では現実的でない
このように、「共通の前提」が存在しない世界で仕事をしている以上、“理解されること”“思った通りに進むこと”を前提に動いてしまうと、必ず裏切られます。
「なぜ伝わらないのか」ではなく、「そもそも伝わらないもの」と考えることが必要です。
感情的になった瞬間、あなたの軸がブレる
理不尽に直面すると、当然イライラしますし、不満も湧きます。
でも、その感情に流されてしまうと、
- 「あんなこと言わなきゃよかった」
- 「冷静さを欠いてミスをした」
- 「余計な一言で信頼を失った」
という落とし穴に、簡単にハマってしまいます。
不動産仲介の仕事は、「信用」こそが最大の資産。感情的になることで、信頼が崩れたり、顧客の不安を煽ってしまうと、取り返しがつきません。
「戦うこと」自体が目的になってしまう危険性
理不尽と戦おうとすると、いつの間にか本来の目的――
「お客様を新しいお住まいを無事に見つけること」
「円滑な契約・決済を実現すること」
これらが見えなくなってしまうことがあります。
「自分の主張が通るかどうか」
「相手を論破できるかどうか」
そうした小さな“勝ち負け”に気を取られてしまうと、本当に守るべきもの(顧客との信頼や全体の流れ)を見失ってしまうのです。
“戦わない”ことは、諦めではない
ここで誤解してほしくないのは、理不尽に対して「戦わない」=「我慢する」「黙って飲み込む」ことではない、という点です。
大事なのは「構造を理解したうえで、最適な道を選ぶ」ということ。
- 感情で返さず、事実と選択肢で返す
- 相手のルールを先回りして把握する
- 無理を通さず、調整可能なところを見極める
つまり、戦いではなく“整える力”が求められているのです。
理不尽の中でどう立ち振る舞うか?

理不尽は、なくならない。だからこそ大事なのは、「理不尽を前提として、どう立ち振る舞うか?」というプロとしての振る舞い方だと述べてきました。
ここからは、現場で今日から意識できるマインドとアクションを整理していきます。
理不尽は「異常」ではなく「前提」として捉える
繰り返す通り、まず、理不尽に直面したときに一番大切なことは「これは“おかしいこと”ではなく、“起こる前提だった”」と捉えること。
- 売主が直前で条件を変更してきた
- 他社営業が顧客に余計なことを言ってトラブルになった
- お客様が、まるで別人のように態度を変えてきた
こうした出来事に驚くのではなく、「それが仕事」と捉える。
心構えひとつで、動揺の度合いが、まるで違います。
常に、理不尽=“想定外”ではなく、“想定内”にしておく。これがプロとしての基本マインドです。
主観ではなく、“構造”と“役割”で物事を捉える
理不尽に感情をぶつけたくなるとき、一度視点を切り替えてみてください。
たとえば…
- 売主仲介担当が高圧的な態度を取ってくる
→ 「彼には時間がなく、上司からのプレッシャーがあるのかも」 - 売主が細かい指摘ばかりしてくる
→ 「多額の資産を売る不安が、苛立ちとして表れているのかもしれない」 - 上司が理不尽に詰めてくる
→ 「会社の責任を背負っているから厳しくなる」
このように、“人”ではなく“構造と役割”に目を向けると、「理解」が生まれ、「感情的な反発」が薄れていきます。
理解しろ、とは言いません。“理解しようとするスタンス”が、自分を守ります。
理不尽の中で“通訳者”になる
あなたの役割は、単なる営業ではありません。
「各当事者の“ルールと言葉”を翻訳する通訳者」です。
- 銀行の専門用語やプロセスを、お客様にわかりやすく説明する
- お客様の感情や意図を、関係各所に誤解なく伝える
- 取引先の意図を読み取り、自社内でうまく調整する
言葉の意味だけでなく、その裏にある「前提・価値観・立場」までも汲み取って翻訳する。
それができる人は、理不尽という構造の中で潤滑油のような存在になれます。
「正しさ」よりも、「流れ」を優先する
理不尽なことがあったとき、「これは間違ってる」「これはおかしい」と、つい正しさを主張したくなります。
でも、覚えておきたいのは:
不動産営業の仕事は、“正しさ”を証明することではなく、“流れ”を止めないこと。
- 誰かを責めている時間があるなら、次に何をすべきかを考える
- 言いたいことをグッとこらえて、全体がスムーズに進むように調整する
- 自分の感情よりも、相手の納得と着地を優先する
この「流れ重視」の判断ができると、結果として、トラブルが減り、顧客満足度が上がり、信頼が蓄積されて、結果もついてきます。
“感情の反射”ではなく、“プロの選択”をする
プロとは、「冷静に選択できる人」です。
理不尽な状況での対応は、大きく2種類に分かれます。
| 感情の反射 | プロの選択 |
|---|---|
| 言い返す | 沈黙して整理する |
| 相手を責める | 背景を確認する |
| 押し切る | 代替案を提示する |
| 怒る | 受け止めてから交渉する |
この違いが、“信頼できる営業”と“トラブルを起こす営業”の境目です。
もし、思い当たる節がある人は「自分は今、反射で動いていないか?」と問い直すクセを持ちましょう。
不動産仲介業における“本当のプロ”とは

理不尽は避けられない。それでも、トラブルの数は“減らすことができる”。
そして、それを日々積み重ねている人こそが、「本当のプロ」と呼ばれる存在です。
では、理不尽だらけの不動産取引において、どうすれば“未然にトラブルを防げる”のでしょうか?
1)相手の“ルール”を先に把握する
トラブルの多くは、条件やルールを「後から初めて知った」という、認識のズレから始まります。
- 他社の取引ルール
- 銀行の融資条件・必要書類
- 売主側がNGとしている条件
- 顧客の「心の中の当たり前」
こうした情報を、「後で確認」するのではなく、“先に予測し、聞いておく”ことが最大の防御です。
- 値下げ交渉が通る余地はあるのか?
- 銀行審査に時間がかかる可能性は?
- 契約までに必要な書類やフローは何か?
- 担当者の判断範囲はどこまでで、誰の承認が必要なのか?
- 引き渡し時期にズレが出た時の対応は?
- このお客様は、何を「絶対に譲れない」と思っているのか?
- 銀行や司法書士の動きに、スケジュール上のネックはないか?
先に聞く。
先に把握する。
先に調整する。
これだけで、理不尽の多くは「理不尽になる前」に整えられます。
2)“起こりうる未来”を事前に設計しておく
プロは常に、「起こるかもしれない未来」を想定しています。
- 売主が契約条件を変えてくるかもしれない
- 銀行が追加書類を求めてくるかもしれない
- お客様の気持ちが冷めるかもしれない
そういった“あり得る未来”に対して、「このときはこう対応しよう」と想定を用意しておく。
それだけで、心の余白と判断の精度がまるで違います。
3)「言った/聞いてない」問題をつくらない
そしてプロは、確認の質と量が圧倒的に違います。
- 書面やメッセージで確認を残す
- 口頭でも伝えて、さらに質問して相手の理解度を確認する
- 一方的に話さない、“双方向確認”を徹底する
勝手な解釈、勝手な思い上がりで仕事を進めない。
この“丁寧な確認”こそが、理不尽を未然に防ぐ最強の盾です。
4)“不測の事態”でも、感情ではなく構造で動ける
しかし、どれだけ準備しても、100%防げるわけではありません。
それでも最後の境界線は――
「感情で対応するか」「構造として動けるか」です。
- 怒るのではなく、要因を分解する
- 責めるのではなく、再発を防ぐ策を考える
- 愚痴をこぼすのではなく、次の動きを設計する
トラブルの時ほど、「人格」ではなく「構造」に目を向けられるか?
それが、“プロの証”です。
5)「トラブルを防ぐ力」が、“信頼”を生む
信頼は、“すごい提案”や“うまい説明”ではなく、「トラブルにならなかった」ことの積み重ねで生まれます部分も大きいのです。
- 想定外がなかった
- 不安が途中で消えていった
- 気づけば、安心して契約を終えていた
こうした「何もなかったこと」の裏には、プロの丁寧な設計と調整の力があるのです。
プロとは、「見えない地雷」を先に見つける人である
何度も言うように、理不尽を避けることはできません。
でも、理不尽を“予見”し、“整える”ことで、最小限に抑えることはできます。
プロの仲介営業とは、言い換えれば「見えない地雷を先に確認し、この先を安全に歩ける地図を描ける人」です。
そのために必要なのは
▶︎先回りして相手のルールを知る力
▶︎立場を超えて構造を理解する視点
▶︎感情を整えて通訳者になれる冷静さ
そういった姿勢こそが、“理不尽の中で戦えるプロ”の条件なのではないでしょうか。
まとめ:理不尽の中で“仕事をする”ということ

不動産仲介営業という仕事は、とにかく「思い通りにいかないこと」の連続です。
どれだけ丁寧に準備しても、どれだけ真面目に取り組んでも、思いもよらないことで止まり、ズレ、揉める。
でも、そのすべてを「理不尽だから」で片づけてしまうと、この仕事を好きになることも、信頼を得ることも、難しくなってしまいます。
大切なのは、「あなたの正義」よりも「冷静に整えること」。
そしてそれは、誰よりも早く“相手の地図”を理解しようとする姿勢から始まります。
この世界は、理不尽なまま変わりません。
でも、その中で“どう戦うか”を選べるのは、自分だけです。
あなたがプロとして一歩踏み出すために・・・
「理不尽と戦うな。理不尽の中で戦え。」
それが、不動産仲介の“本当の仕事”です。